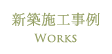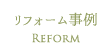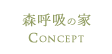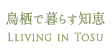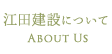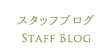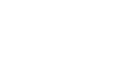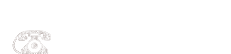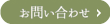相手に頼みごとをする際、気軽に言える人には「それを取って頂戴(ちょうだい)」「早くして頂戴」など、「下(くだ)さい」のかわりに「頂戴」を使います。
また対照的に、自分が何かをいただく時の「十分頂戴しました」「食事を頂戴いたします」など、丁寧な言葉使いの「頂戴」もあります。
この「頂戴」も本来は仏教語で、もともとは仏さまの教えである経典を、頭の上に載せ頂くことを意味しており、最高の敬意を表す行いのことです。
浄土真宗でよく唱えられる『十二礼(じゅうにらい)』に「観音頂戴冠中住(かんのんちょうだいかんちゅうじゅう)」とあり、
これは観音様が冠を頭の上に戴かれ、その冠の中に、仏が住んでいると説かれています。
頂戴とは、本来、頭の頂にのせることを言い、仏様の教えを、頭にのせていただくことなのです。
それが、物をもらった際にその物を頭に頂く行為となり、それから物を頂く時に使われるようになりました。
目よりも高くささげ、頭を低く下げてもらう「いただき物」。頂戴物(ちょうだいもの)とは、いただき物のことを示します。
「食事を頂戴いたします」は「いただきます」と同じ意味でしょう。
肉をはじめとして野菜・穀物など、動植物のいのちを頂くことで、私たちは自らの命を維持しています。
さらに、その食事が食卓に上るまでは、農業や漁業・畜産業、あるいは流通や加工・調理に関わる方々、
そしてご家庭の場合はそれを料理するご家族等々、多くの皆さまの手を経ています。
食事のはじめの「いただきます」は、動植物のいのちを頂戴し、多くの皆さまの手間を頂戴しますという感謝の言葉といえましょう。
参考 『曹洞宗関東管区教化センター』HP、『妙法寺』HP、『築地本願寺』HPほか
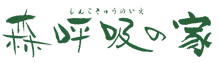




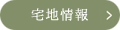

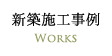


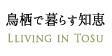






 2025年12月21日
2025年12月21日