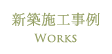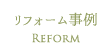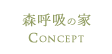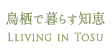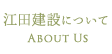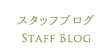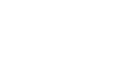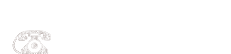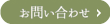食後の挨拶である「ごちそうさま」の“ちそう(馳走)”とは、元々は漢語で「馬で走り回る」ことを意味する言葉でした。
その昔は大切な客人を迎える時にその準備のため、方々へ馬を走らせ食材を調達しなければなりませんでした。
その様子から日本では「馳走」という言葉が「もてなし」を意味するようになり、さらに「馳走」に敬語の「御」を付けた「御馳走」は、
もてなしのための豪華な料理を意味する言葉となったそうです。
また仏教では、仏教および仏教徒を守護する神が教えられています。
その中に「韋駄天(いだてん)」が出てきます。
昔、足の速い人がいると「韋駄天のようだ」、また「韋駄天走り」と言われました。
その韋駄天がお釈迦さまの為に駆け回って食材を集めてきたという話があります。
仏教では、この韋駄天の話から、食事だけではなく、他の人の為に奔走(ほんそう)して、苦しんでいる人を助けることをも「馳走」と言います。
仏教の開祖お釈迦さまは35歳の時に仏のさとりをひらかれて80歳でお亡くなりになるまでの45年間、インドを「馳走」されました。
浄土真宗の開祖親鸞聖人は29歳の時に阿弥陀仏の本願に救いとられ、本当の幸せになられてから、
90歳でお亡くなりになるまで、京都、新潟、関東を「馳走」されました。
そのような「馳走」される仏教の先生がおられたからこそ、2600年の時代と国を超えて、今日、日本に仏教が伝えられています。
お釈迦様から渡された仏教というバトンが、インドから中国、中国から日本へとつながり、今日、私のところまで届けられたのです。
まさに「馳走」のおかげです。
そう思いますと「ごちそうさまでした」は、食事の感謝の言葉でありますが、私が仏教と巡り合った感謝の言葉ともいえるかもしれません。
仏の教えを聞くことができたことに感謝して「ごちそうさまでした」。
参考 『三菱商事ライフサイエンスの味な話』HP、『1から分かる親鸞聖人と浄土真宗』HP、『ぶつだんやさん』HPほか

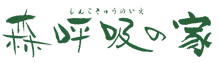




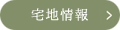

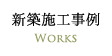


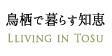






 2025年12月21日
2025年12月21日